第7回 大賞作品
忘れられた歩道橋 小田中 準一(千葉県 68歳)
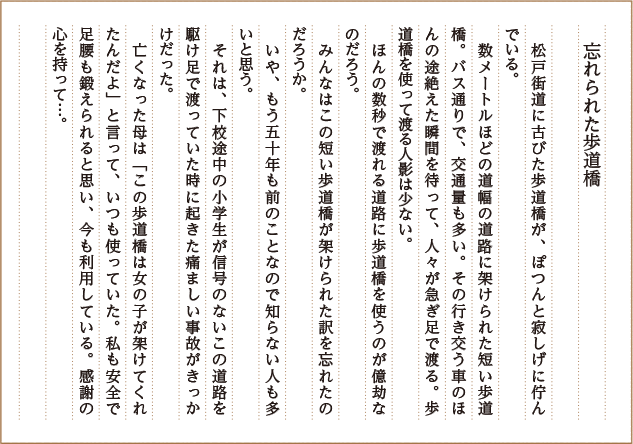
そう、人間って忘れっぽい
選定委員:栗田 亘(コラムニスト)
そういえば、影が薄れた古い歩道橋が結構あるなあ。文章を読んで、思い当たりました。
昭和40年代(1965年~1974年)を中心に、各地で次々に歩道橋が誕生しました。交通事故による歩行者の死傷が激増した時代です。
いま全国で1万1千超あるそうです。おそらく世界最多。欧米では、街並みと調和しないとされ、類例は多くはないと聞きます。
日本では歩道橋の効果は大きかった。加えて、歩道の整備、横断歩道の設置なども進み、歩行者の死傷事故は減少に転じました。
すると、歩道橋の欠点が指摘されるようになった。上り下りがとくにお年寄りやベビーカーのお母さんにはきつい、車いすでは利用できないなどと。歩道橋そのものが「バリア」になっている。景観も妨げている。老朽化に伴って撤去された歩道橋も出てきました。
人間とは忘れっぽく勝手でもある。そこに目を留めた小田中さんは的確でした。聞けば小、中学校の社会科の先生だったとか。
昔、中学生のとき、社会科の先生の授業が面白くて、世の中と直接つながっている教科だと思った。それで同じ道を選んだそうです。
現場の歩道橋に行ってみました。階段は片側30数段。なかなかきつい。1967年の建設で、トシではあるし、弱者に優しくないし、不格好です。けれどそれなりの利用価値はあるし、補修もされている。
向こう側に渡りまた戻りつつ、安全とは?便利とは?不便とは?あれこれ考えさせられました。
昭和40年代(1965年~1974年)を中心に、各地で次々に歩道橋が誕生しました。交通事故による歩行者の死傷が激増した時代です。
いま全国で1万1千超あるそうです。おそらく世界最多。欧米では、街並みと調和しないとされ、類例は多くはないと聞きます。
日本では歩道橋の効果は大きかった。加えて、歩道の整備、横断歩道の設置なども進み、歩行者の死傷事故は減少に転じました。
すると、歩道橋の欠点が指摘されるようになった。上り下りがとくにお年寄りやベビーカーのお母さんにはきつい、車いすでは利用できないなどと。歩道橋そのものが「バリア」になっている。景観も妨げている。老朽化に伴って撤去された歩道橋も出てきました。
人間とは忘れっぽく勝手でもある。そこに目を留めた小田中さんは的確でした。聞けば小、中学校の社会科の先生だったとか。
昔、中学生のとき、社会科の先生の授業が面白くて、世の中と直接つながっている教科だと思った。それで同じ道を選んだそうです。
現場の歩道橋に行ってみました。階段は片側30数段。なかなかきつい。1967年の建設で、トシではあるし、弱者に優しくないし、不格好です。けれどそれなりの利用価値はあるし、補修もされている。
向こう側に渡りまた戻りつつ、安全とは?便利とは?不便とは?あれこれ考えさせられました。
