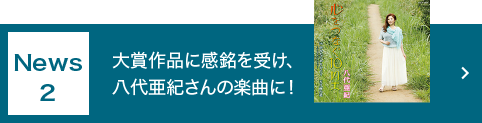第1回 大賞作品
命をつなぐ十円玉 芦田 薫(兵庫県 48歳)
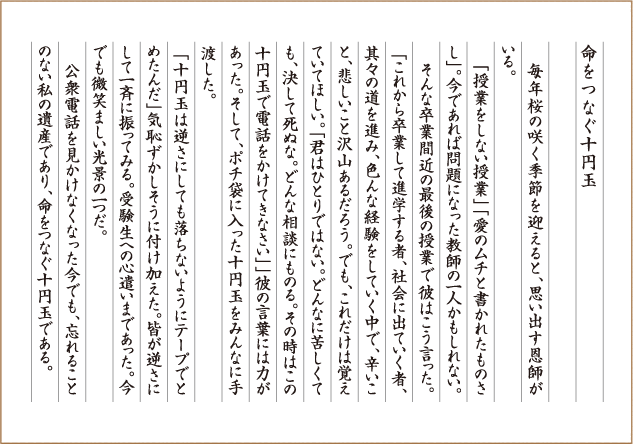
今、伝えなければ。
選定委員:
くだんの先生は担任ではなく、始終話が脱線する、人気の国語教師だったそうだ。
窓の向こうには緑の木々が葉を揺らし、春風がそよぐ3月。
「今日は最後の授業だね」と言って教壇に立った。授業が終わるころ、教師はひとりひとりの名前を読み上げ、ポチ袋を渡した。「いつにない特別に強い声で、絶対に死ぬな、と言いました。何があっても、どんな相談にも乗るからと。今伝えなければという、強い使命感みたいなものを感じました」と、芦田さんは振り返る。
高校の合格発表前のことである。10円玉が袋から落ちては縁起でもないと、ひとつひとつ袋の内側に貼り付けてあった。
高校、短大と、芦田さんはそのポチ袋を電車の定期入れに挟んで持ち歩いた。
「そのうちだんだん袋がよれてきたので、おもちゃの鍵付き宝箱に入れました。でも、子どもの自殺のニュースを見るたび、思い出すんですよね、あの10円玉を」
心の中に、いつも先生の言葉が寄り添っていた。だが、今は持っていない。
「阪神淡路大震災の2?3年後のことでしょうか。いくつめかの職場で働いていたあるとき、宝箱を開けたら袋が破れていて。もういいかなって思ったんです。先生の気持ちは充分に受け取れた、私の心の中にはいつもあるからいいなって。でも他の10円と一緒にするわけにはいかない特別なもの。だから、神社のお賽銭箱に納めました」
十数年前に手放した10円玉のことを今回書こうと思ったのには、わけがある。
「使命感から、でしょうか。あいかわらず子どもの悲しいニュースは減らないから。今、伝えなくちゃって強く思って、締めきりの前日に書きあげたのです」
きっと10円玉先生は、誰の心にもひとりはいるし、今も日本中にたくさんいる。そういうことを今伝えなくてはと私も思い、この作品を選ばせてもらった。
受賞者インタビュー
十円玉は、今でも
私の心の中にあります。
「わたし遺産」に応募しようと思った「きっかけ」をお聞かせください。
日々、先生側が原因の学級崩壊や自殺の問題などがニュースで報じられていて、私自身、知人の先生が精神的にまいってしまい相談をされるなど、いつから教育現場はこのようになってしまったんだろうとずっと気になっていたんです。だからどこかで、恩師のこの話を伝えたいなと思っていて、この機会に書いてみよう、書かなくてはと思いました。
作品の先生はどのような方だったのでしょうか?
「愛のムチと書かれた物差し」というのは、30cmぐらいの竹でできているのですが、裏に「愛のムチ」と本当に書いてあるんです。だからと言ってそれで体罰をする訳ではなく、怒られる時もそれで頭を軽くポンとやるぐらいで、普段から優しくて温厚な先生でした。勉強する時はする、怒るときは怒るなどメリハリがすごかったですが、授業が楽しいから生徒も萎縮しなかったですし、お互いに愛情や信頼関係がありました。
作品で取り上げられた時代に対する思いをお聞かせください。
不便でしたが、あの時代に対する想いは強いです。公衆電話がなくなっていくに連れて、ああ、あの十円玉も使えなくなるなと感じたり…。今は情報的には便利ですが、知識に振り回されて知恵がなくなっているようにも思います。でも、私がこの作品を締めきりギリギリに応募できたのはネットがあったからなんです。昔のことでも伝えられることはきちんと伝えつつ、それぞれの時代のいいところを生かしていくのが一番いいなと思います。
大賞に選ばれた時のお気持ちをお聞かせください。
最初に聞いた時は信じられない気持ちでビックリしました!書いたのは初めてですし、私は全然本も読みませんでしたので、実感がわかなかったです。でも、「わたし遺産」のテーマにはピタリと合った気はしました。公衆電話もなくなってきていますが、十円玉を見ると公衆電話を連想します。それもありました。
十円玉を通して昔の時代と今がつながる感じがしています。
今回の受賞や取材・撮影を振り返られて、ご感想をお願い致します。
楽しくてワクワクしましたが、まだ信じられません。でも、今回の企画は、自分の新たな1ページを開いていくきっかけになったと感じています。これからも何か書いて伝えられることは伝えていけたらいいなとも思っています。もう作品の十円玉はありませんが、十円玉を見るたびに先生の熱意を思い出します。カタチとしてはなくても、今でも私の心の中に先生の十円玉はしっかりとあります。