第1回 大賞作品
八丈ショメ節 沖山 芙美子(神奈川県 66歳)
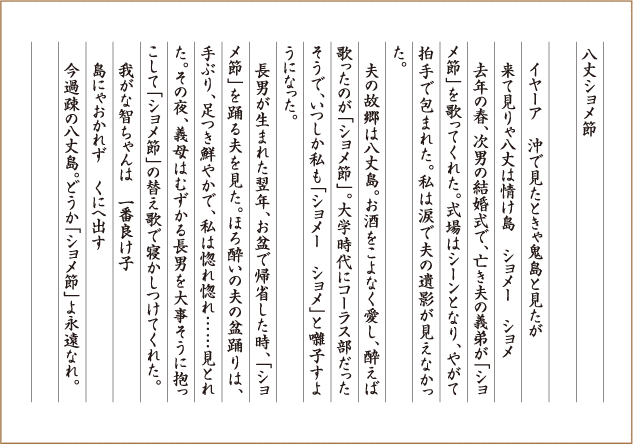
「即興詩」の素晴らしさ
選定委員:栗田 亘(コラムニスト)
〽よくか生きたれ長生きしたれ こんな嬉しいことはない ショメー ショメ
新婦のおばあさまが出席しているのを見ての、とっさの機知でした。
日本全国で歌われる民謡は、5万とも6万ともいわれる。それぞれの歌に、その土地ならではの味わい、歴史がにじんでいますが、ショメ節の面目(めんぼく)は「即興」にあります。〽我がな智ちゃんは一番良け子…という子守歌のように。
場の雰囲気、自分の気持ち、相手の心情、暮らしの哀歓。人間は笑い、祝い、恋し、涙します。歌い手はそれらを受けとめ、即興で自分の言葉を歌の翼にのせるのです。伝えられている詞は800を超え1000に及ぶらしい。
八丈島に出かけて、菊池さんに会いました。東京から南に290キロメートル、黒潮に囲まれたこの島で観葉植物を栽培しておられる。とともに、島で指折りのショメ節の名人上手です。65歳。突き抜けるような高い、澄んだ声の持ち主です。
〽南風だよ皆出ておじゃれ 迎え草履(ぞうり)の紅鼻緒(べにはなお) ショメー ショメ
役場が編んだ『八丈町誌』によれば、ショメ節は明治中期に盆踊り唄として生まれました。けれど島の歌い手たちは、もっと古い時代に、流人や漂着者、江戸と八丈島を行き来した御用船の船乗りたちが伝えた各地の民謡を、島人が八丈ならではの歌と踊りに綴り合わせた、と言います。ボクはこちらを信じたい。
囃子(はやし)ことばの「ショメ」は、食べ物の味付けに使う「塩と梅」のこととか。なんとも味わいのある歌、という心意気のようです。
即興詩は、ウイットとユーモアを伴います。ふたつとも、やわらかい余裕がなければ生まれません。かりにお金が乏しくても思いが豊かならば、心に響く即興詩が生まれるに違いない。
〽ここの座敷はめでたい座敷 四つの隅から黄金湧く ショメー ショメ
「即興詩人」がもっともっと増えますように。
受賞者インタビュー
八丈島の言葉を残し、
伝えていきたいです。
「わたし遺産」に応募しようと思った「きっかけ」をお聞かせください。
夫が八丈島の出身で、夫はいずれは島に帰りたいと考えていました。病気で亡くなりましたが、島のことを子どもたちににきちんと伝えていかなくてはと考えていたんですね。私は八丈島のショメ節というものがすごく耳に残っていて、だからショメ節を代表的なものとして、夫の島の思い出を書きたい、思い出の島の言葉を残したい、それを次の世代に長く伝えていけたらという思いで書きました。
ご主人様はよくショメ節を唄われていたのでしょうか。
お酒を飲むと唄ってくれる時がありました。夫は中学、高校の時には八丈島で野球をやっていたのですが、大学ではコーラス部に所属していたので、とてもいい声でした。
八丈島での思い出や、八丈島に対する思いをお聞かせください。
八丈島は、機会があれば行ってみたいなと思っていたぐらいで、結婚するまではまったく縁がありませんでした。異国とまでは言わないまでも、スコールのような雨や湿気も多く亜熱帯のような所で、人ものんびりしているし沖縄のような印象でしたね。島の人は一日中海で遊んでいるような感じで、こっちものんびりできるのがいいんです。八丈島は宇喜多秀家が流された島で、色々な歴史的な見所もあるんですよ。そして、島独自の島言葉がまだ生きていて、面白い方言がずっとのこっている所です。島は4つの地区があるんですが、その地区だけの言葉ものこっています。今は、それを次の世代に長く伝えていけたらと思っています。
大賞に選ばれた時のお気持ちをお聞かせください。
ショメ節を残したいという気持ちで書きましたが、関係者の方に読んで知ってもらえたらそれでいいという感じだったので、大賞なんてとんでもないという気持ちでビックリしました。でもこれを、子どもたちには読んでもらいたいと思っています。
今回の受賞や取材・撮影を振り返られて、ご感想をお願い致します。
取材も撮影もまるっきり初めてだったので、どうなるものかなと思っていましたが、選定委員の栗田さんは八丈島に詳しくとても懐かしかったです。親しみがわいて、私も嬉しくなりました。こういう機会をいただけて、凄くリラックスしてお話も聞いていただき、楽しく過ごせてよかったです。
