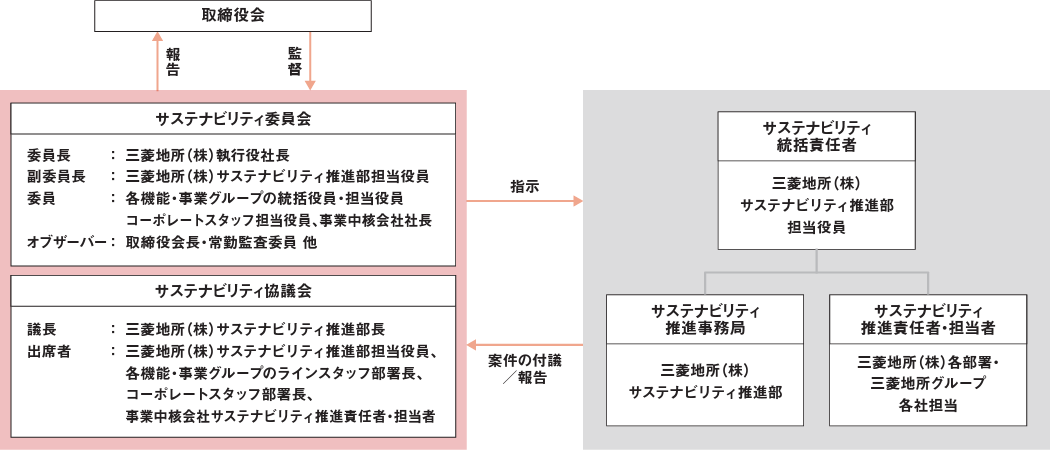| 1 |
Environment
気候変動や環境課題に積極的に取り組むまちづくり |
- 目標
-
2030年までにCO2排出量(Scope1+2+3)を35%削減する(2017年度比)
※2022年度以降、以下に変更。
「2030年までにCO2排出量(Scope1+2)を70%以上、CO2排出量(Scope3)50%以上削減する(2019年度比)」
- KPI
-
※2022年度以降、以下に変更。
「CO2排出量(Scope1+2)」
「CO2排出量(Scope3)」
|
2017年度比▲24.0%(2,534,820t-CO2)
(参考:新目標対比)
- Scope1+2排出量:2019年度比▲34.5%(312,198t-CO2)
- Scope3排出量:2019年度比▲37.6%(2,222,622t-CO2)
|
- Scope1+2排出量:2019年度比▲44.3%(265,442t-CO2)
- Scope3排出量:2019年度比▲48.5%(1,833,828t-CO2)
|
- Scope1+2排出量:2019年度比▲52.9%(224,239t-CO2)
- Scope3排出量:2019年度比▲42.4%(2,053,137-CO2)
|
- Scope1+2排出量:2019年度比▲54.8%(215,096t-CO2)
- Scope3排出量:2019年度比▲47.5%(1,868,788t-CO2)
|
- 目標
-
2050年までにCO2排出量(Scope1+2+3)を87%削減する(2017年度比)
※2022年度以降、以下に変更。
「2050年までにCO2排出量(Scope1+2+3)においてネットゼロを達成」
- KPI
-
※2022年度以降、以下に変更。
「CO2排出量(Scope1+2+3)」
|
2017年度比▲24.0%(2,534,820t-CO2)
(参考:新目標対比)
- Scope1+2+3排出量:2019年度比▲37.2%(2,534,820t-CO2)
|
2019年度比▲48.0%(2,099,270t-CO2)
|
2019年度比▲43.6%(2,277,376t-CO2)
|
2019年度比▲48.4%(2,083,884t-CO2)
|
- 目標
-
2030年までに再生可能電力の使用比率を25%とする
※2022年度以降、以下に変更。
「2025年度までに再生可能電力の使用比率を100%とする」
|
|
|
|
|
- 目標
-
2050年までに再生可能電力の使用比率を100%とする
※2022年度以降、上記目標の更新に伴い本目標は廃止。
|
|
|
|
|
- 目標
-
2030年までに食品・プラスチックを中心とした廃棄物再利用率を90%とする
|
|
|
|
|
- 目標
-
2030年までに㎡あたりの廃棄物排出量を20%削減する(2019年度比)
|
|
|
|
|
| 2 |
Diversity & Inclusion
暮らし方の変化と人材の変化対応しあらゆる方々が活躍できるまちづくり |
- 目標
-
2030年度までにオフィスや住宅等の建設時に使用する「型枠コンクリートパネル」における、持続可能性に配慮した調達コードと同等の木材利用比率を100%とする
- KPI
-
「型枠コンクリートパネル」における、持続可能性に配慮した調達コードと同等の木材利用の推進状況
|
要件を満たす木材利用比率100%を達成するため、三菱地所㈱が発注する新築工事に関し、施工者宛に本件木材の利用を見積要項書等で順守頂くよう依頼している。
|
- 前年度に引き続き、三菱地所㈱が発注する新築工事に関し、施工者宛に本件木材の利用を見積要項書等で順守頂くよう依頼している。
- 2022年度は二次サプライヤー以降の取引先を含め施工会社43社、清掃会社17社、計60社にヒアリングシート調査を実施。さらに、施工会社に対しては、調査回答後にサプライヤー企業で働く従業員へのインタビューも実施。
- 持続可能性に配慮した調達コードと同等の木材利用比率:80%(2030年目標対比)
|
- 2023年度より清掃会社へのインタビューを開始。
- 2023年度は、二次サプライヤー以降の取引先含め施工会社22社、清掃会社4社、計26社にヒアリングシート調査を実施
|
持続可能性に配慮した調達コードと同等の木材利用比率:81%
|
- 目標
-
※2022年度以降、以下に変更。
「女性管理職比率を2030年度までに20%超、2040年度までに30%、2050年度までに40%とする」
|
|
|
|
|
- 目標
-
2025年度までに管理職候補である係長級の社員に占める女性労働者の比率を30%程度とする
※上記目標の改定に伴い、同社方針により本目標は非開示項目となったため、本目標は上記目標に集約されたものとみなし、削除。
|
|
|
|
|
- 目標
-
2030年度までに男性の育児休業取得率を100%とする
- KPI
-
男性の育児休業取得率
※2021年度以降の算出定義:「当該年度の間で配偶者が子を出産した男性社員の数(a)」に対する「同年度中に新たに育児休業をした男性社員数(b)」の割合(b/a)。(b)には、当該年度より前に子が生まれたものの、生まれた年度内に取得せず、当該年度になって新たに取得した社員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。
|
|
|
|
|
- 目標
-
2030年度まで毎年、女性の育児休業取得率を100%とする
|
98.7%
※特殊事情により1名が未取得となったもの。
|
|
|
|
- KPI
-
ホスピタリティの強化とストレスフリーシティの実現に資する取り組みの具体的進捗状況
|
- 2021年11月、多言語対応のヘルスケアサービス「WELL ROOM」を開始。中小企業やスタートアップ企業を主な対象として、多言語・多文化に対応した健診実施医療機関の紹介やメンタルヘルス相談サービス、産業医相談サービスを提供。
- 2022年3月、「働く女性ウェルネス白書2022」を発表。丸の内エリアを中心とした約300名の働く女性を対象に、キャリアやライフイベントに関する価値観・就労環境等のアンケート調査と取得した健診結果データをクロス集計し公表。
- 2022年10月、「有楽町アートアーバニズムプログラム YAU」第2期活動を開始。有楽町ビル10階の約1,200㎡をアーティストの創作活動拠点として、再開。アートとビジネスの核となるコミュニティの形成等が狙い。
- 2022年12月、東京藝術大学と包括連携協定を締結。両社で、芸術の力を人・企業・まちへと還元し、社会課題の解決に寄与することを目指す。
|
- 同社グループのサプライチェーン上で働く外国人を中心とした就業者の労働者の労働環境・生活環境の更なる改善や、人権尊重の強化を目指し、二次以降の取引先を含め施工会社5物件において43社、清掃会社17社、計60社にヒアリングシート調査を実施。更に、サプライヤーのサステナビリティ推進状況を正しく理解すべく、施工会社においてはヒアリングシート調査回答後に、サプライヤー企業で働く労働者へのインタビューを実施。なお、違反事項は全体を通じて0件。
- 2023年3月、産学医連携プロジェクト「働く女性 健康スコア」を公開。神奈川県立保健福祉大学の協力のもと、異業種14社の計3,400名の回答結果に基づく調査。「女性の働きやすい環境、その為の文化醸成」を目指すもの。
|
- 同社グループのサプライチェーン上で働く外国人を中心とした就業者の労働環境・生活環境の更なる改善や、人権尊重の強化を目指し、2023年度はサプライヤーへのヒアリングシートに加え、新たに施工現場及び清掃現場の就業者への対面インタビューを実施。
- 一般社団法人JP-MIRAIが運営する外国人労働者相談・救済窓口サービスの「JP-MIRAIアシスト(電話、アプリ、対面等の方法で、外国人労働者から仕事面のトラブルに留まらず、生活・教育・医療・福祉など、様々な領域にわたる相談を多言語(9カ国語、2023年9月時点)で受け付け、当事者に寄り添い、解決を目指すサービス)」を業界として初導入。なお、一般社団法人JP-MIRAIと協働し、2024年3月現在、約20プロジェクトにて導入中。
- 2023年6月、睡眠不足や育児不安に悩む母親・家族サポートとして、大手デベロッパーで初めて、ロイヤルパークホテルにて、「都心宿泊型産後ケアサービス」の試験運用を開発。
- 2023年、「休憩室シェアリング事業」として、大手町ビルにて「とまり木」実証実験開始。
- 2024年3月、働く女性が自分自身と向き合う時間をつくること、そして対話することの大切さを再認識することを目的としたウェルネスイベント「Will Conscious Marunouchi 2024 まるのうち保健室 〜私と向き合う時間〜」を開催。
|
- 2025年4月、テナント従業員のリカバリー機能に対する需要の高まりに着目し、心身のリフレッシュに寄与するチャージ機能を備えた休養室の企業間シェアサービス、「とまり木」を本格提供開始。
(2023年10月より試験運用)
|
| 3 |
Innovation
新たな世界を生み出し続ける革新的なまちづくり |
- 目標
-
AI・ロボティクス等の最新テクノロジーの活用や、その他新規事業などをノンアセット事業の「新規領域」と位置付け、外部企業等とも連携のうえ、サステナブルな社会の実現に貢献する新たなビジネスモデル・事業機会の創出を目指す
- KPI
-
新事業創出、デジタルビジョン、ロボティクス技術の活用ならびに「大丸有SDGs ACT5」の取り組みの具体的進捗状況
|
- 2022年1月、5Gインフラシェアリング事業へ参入。街全体での5Gのエリア化を、共用の鉄塔・屋上ポール等インフラで実現。国や全国の自治体、不動産オーナーと連携しながら、次世代のまちづくりの基盤となる5Gインフラの構築に取り組み。
- 2022年3月、中長期的な社会インパクトの創出に挑むスタートアップへ投資する「BRICKS FUND TOKYO」を開始。今後5年間で国内外のスタートアップに100億円程度の出資を想定。
- 2022年2月、顔認証サービス「Machi Pass FACE」開始。
- 2022年2月、「Machi Pass」と電動キックボードシェアアプリ「LUUP」との連携を開始。
- 2021年11月、丸の内エリアに「次世代カメラシステム」を導入。①個別ビル毎に実施していたカメラの制御・管理を丸の内エリア全域で一括実施、②複数ビルに跨って、最先端のAI画像解析をセキュアに実施、③混雑状況の把握やお困りの方へのサポート、災害時の被害状況の把握等まちづくりに活用等の効果が期待できる。
- 2022年1月22日~25日に、丸の内仲通りアーバンテラスにて、3Dデジタルマップによるロボット走行環境形成の実証実験(遠隔注文→ロボットによるテーブル配送)を実施。
- 「大丸有SDGsACT5」:延べ参加人数10,507名(2か年累計約19,000名)、新規参加企業数68社(2か年累計120社超)、ポイントアプリ登録者数2,217人
ACT1(サステナブル・フード):「SUSTABLE~未来を変えるひとくち~」を2021年9月より全6回のプログラムで開催。
ACT2(気候変動と資源循環):服から服をつくるプロジェクト「BRING」(大丸有エリア内の複数拠点に不要になった衣類回収ボックスを設置し6ヶ月間で約500kgの衣類を回収し再資源化)、ソーラーシェアリングにみる未来のエネルギーの可能性を学ぶオンラインセミナー・視察会、九十九里浜でのプロギング等各種活動を実施。
ACT3(WELL-BEING):ACT5歩数チャレンジ(「毎日の歩数」と「SDGsの取り組みへの参加」をスコア化した個人戦を開催。延べ373名が参加。)、慶應義塾大学大学院前野教授と連携し「暮らす街の幸福度調査」を実施。
ACT4(ダイバーシティ&インクルージョン):2021年11月にD&Iの取組を一歩進めるためのAllyコミュニティ「E&Jラボ」設立。
ACT5(コミュニケーション):「大丸有SDGs映画祭2021」開催、国際芸術祭「東京ビエンナーレ2020/2021」アートプロジェクトと連携したSDGs啓発の取り組み。
|
- 2022年11月、スマートホームサービス「HOMETACT」について㈱LIXIL・mui Lab㈱と連携。CO2排出量削減に資するHEMS機能開発を共同で推進。
- 2002年に開設・事業支援を進めていた「東京21cクラブ」をリブランディングし、2022年12月に「The M Cube」として再スタート。合わせて、新丸ビル10階の施設「EGG JAPAN」を増床等のリノベーションを行い「EGG」と改称。会員制度の見直しを含め、スタートアップを中心とするオープンイノベーションコミュニティとして、更なる新事業創出支援を推進。
- 「The M Cube」と「TMIP」が蓄積してきたネットワークとアセットの高度利用等を目的に、大企業とスタートアップの協業機会を生み出すスタートアップコミュニティ「MiiTS」を発足。
- 「Society5.0」へ向けた取組として、2023年2月より大手町パークビルの同社オフィス執務室内へのロボットフードデリバリーサービスの導入、2022年12月に常盤橋タワーにおいて自律移動型ロボットによるセンサーデータの自動収集・設備点検システムの構築、2023年1月より丸ビル・新丸ビルにおけるAI画像解析を活用した施設運営管理体制の構築。
- 「大丸有SDGsACT5」:5つのACTに紐づく63のアクションを展開。延べアクション参加数16,168名(3ヵ年累計約35,000名)、84社(2021年度対比+16社)とのパートナーシップを実現。ポイントアプリユーザー数2,521人(2021年度対比+304人)。
ACT1(サステナブル・フード):昨年に引き続き「SUSTABLE2022~未来を変えるひとくち~」を全6回のプログラムで開催。
ACT2(気候変動と資源循環):衣類の回収活動「Re;POST」により、延べ約2,500名から総重量約1,350kgの衣類を回収。約88%が国内外でリユースし、焼却処分した場合のCO2排出量1,000kgの削減効果。
ACT3(ひとと社会のWELL):2022年5月から11月(8月を除く)の毎月計6回のプロギングイベントを開催。近隣エリアに拠点を持つ企業との連携を企画したことや平日夕方に開催したこと、三菱地所プロパティマネジメントが企画するエリアを訪れる方々へのおもてなしの取り組み「丸の内アンバサダー」と連携したこと等により取り組みは広がり、毎回約25名が参加し、毎回10㎏を超えるごみを収集。
ACT4(ダイバーシティ&インクルージョン):LGBTQの権利啓発の活動が行われる6月のPRIDE月間にちなみ、オリジナルのレインボーフラッグによる街の装飾と、LGBTQについて楽しみながら“丸の内”で「知る」イベントを開催。LGBTQについて分かりやすく解説したパネル展示や、期間限定「丸の内二丁目BAR」、DJイベント等を実施。トークセッションでは、セクシュアリティも生き方も多様なゲストから、過去から現在に至るまでの心境や体験をお話しいただき、みんなで「多様性とは何か」を楽しく知り、考える機会を提供。
ACT5(コミュニケーション):開催3年目となる「日経SDGsフェス大丸有2022」を対面・非対面のハイブリッドで開催。過去最高となる、257人もの講演者を迎え、5月と9月の12日間にわたり20のイベントを日経ホールと丸ビルホールで実施すると同時に日経チャンネルで配信。全体で4万人が参加・視聴。また、前年度に引き続き「大丸有SDGs映画祭2022」を開催し、初の屋外上映にも挑戦した。
|
- 2023年6月、自動運転技術を活用した次世代物流システム構築を目指す㈱T2と資本業務提携。京都府城陽市で開発中の次世代基幹物流施設における共同開発を推進。
- CVCファンドであるBricks Fund Tokyoでは、モビリティSaaS「Park Direct(パークダイレクト)」を提供する㈱ニーリーや、環境負荷を低減する生分解性ポリマーメーカーZYMOCHEMに出資。
- 2023年6月、同社が賃貸する丸の内エリアのオフィス・店舗で働く就業者向け会員制度「Machi workers」を開始。会員は丸の内ポイントの2%加算や各種イベントへの優待参加等の特典・サービスを受けることが出来、来街したくなる・出社したくなるまちづくりに貢献。
- Machi Pass及び丸の内ポイントアプリなどの基盤整備を完了し、同社グループ内以外の様々なデータを蓄積した分析基盤「SoDA」を活用した事業横断マーケティングに着手。
- 三菱地所サイモン社がデジタル戦略部を新設。プレミアムアウトレットでの購入者を対象にした、ユーザーエクスペリエンスを高めるサービスの提供を企図。
- 「大丸有SDGsACT5」:5つのACTに紐づく62のアクションを展開。延べアクション参加数35,543名(4ヵ年累計約70,000名)、90社(2022年度対比+6社)とのパートナーシップを実現。ポイントアプリユーザー数4,160人(2022年度対比+1,639人)。
ACT1(サステナブル・フード):昨年に引き続き「SUSTABLE2023~未来を変えるひとくち~」を全5回のプログラムで開催。
ACT2(気候変動と資源循環):衣類の回収活動「PASSTO」により、延べ約10,590名から総重量約2,400kgの衣類を回収。約90%が国内外でリユースし、焼却処分した場合のCO2排出量1,666kgの削減効果。
ACT3(ひとと社会のWELL):2023年6月から11月まで毎月計6回のプロギングイベントを開催。今年で3年目となるこのイベントは、徐々に認知度が高まり、1回あたりの参加人数が増えたことに加え、職場の仲間によるグループで参加する事例がふえたことが特色。全6回で、計225名が参加し、53.5㎏のごみを拾った。
ACT4(ダイバーシティ&インクルージョン):未来の多様性について考える イベント「E&Jフェス」を2日間にわたり開催。1日目にはトークイベントを開催。(当事者や有識者、先進的取り組みを進める企業、社会的発信に取り組む方などを招き、多様な働き方・生き方の実践のお話、企業の取り組み事例、「誤解の多いダイバーシティ経営」についてイベントを開催)2日目は、都内で初となるダイバーシティパレードを開催。大丸有エリアの就業者や来街者等にD&Iについて広く知っていただくことを目的に、ビジネスパーソンの“働き方”の歴史を「過去」「未来」に分けて表現。「過去パート」では明治から現代までの働き方の変遷をパネルや当時の服装等で紹介し、「未来パート」では、障がい者やLGBTQ等当事者団体、農福連携、パラアスリート、アライなど多様な人々が一堂に会し、多様な人が活躍できる社会“未来のアタリマエ”を表現。
ACT5(コミュニケーション):「日経SDGsフェス大丸有2023」を対面・非対面のハイブリッドで開催。211人の講演者を迎え、16のイベントを日経ホールと丸ビルホールで実施すると同時に日経チャンネルで配信。全体で1.8万人が参加・視聴。また、「大丸有SDGs映画祭2023」開催。全回満席を達成し(雨天による屋外から屋内への振替回を除く)計700名超が参加。
|
- 自律型警備ロボットの開発・提供を行うSEQSENSE株式会社と連携し、ビル管理業務の効率化を実現。
- 障がい者特化型DX プラットフォーム「NEXT HERO」事業を手掛けるVALT JAPAN株式会社と連携し、「デジタルイノベーションセンター丸の内 supported by 三菱地所」を開設。
- 「大丸有SDGsACT5」:5つのACTに紐づく54のアクションを創出。延べアクション参加数28,219名(5ヵ年累計98,930名)、69社からの協力を実現。ポイントアプリユーザー数は10,771人に増加(昨年度比+6,611人)。
- ACT1(サステナブル・フード):ジビエの普及啓発イベントを大丸有飲食店と連携して開催。
- ACT2(気候変動と資源循環):お濠の生物多様性について学ぶ「濠プロジェクト」を開催。
- ACT3(ひとと社会のWELL):歩いたりジョギングしたりと体を動かしながら、 街に落ちているごみを拾う、北欧生まれのSDGsスポーツ:プロギングイベントを開催。
- ACT4(ダイバーシティ & インクルージョン):未来の多様性について考えるイベント「E&Jフェス」を2日間にわたり開催。2日間で約5,800名が参加。
- ACT5(コミュニケーション):「大丸有SDGs映画祭2024」を開催。紛争やダイバーシティ、気候変動など「いま考えたい世界のコト」をテーマにした長編9作品を上映し、約550名が参加。
|
| 4 |
Resilience
安全安心に配慮し災害に対応する強靭でしなやかなまちづくり |
- 目標
-
建物単独での地震・水害対策や安定的エネルギー供給の構築などに加えて、災害時でも事業継続可能な環境整備や帰宅困難者の一時受入体制の整備などのソフト面に関する取り組みを進め、また、複数ビルの総合運営やエリア内の連携体制の強化を行い、安心・安全のまちづくりを進める
- KPI
-
安心・安全のまちづくりに関する取り組みの具体的進捗状況
|
- 2021年に策定した、「エネルギーまちづくりアクション 2050」に基づき、「スマートエネルギーデザイン部」を中心に、丸の内エリアでコジェネレーションシステムを増強し、エリア内の自営電源の確保の取り組みを推進。
- 災害対策機関での情報共有や帰宅困難者向け情報発信を行うプラットフォーム「災害ダッシュボードBeta」の実証実験を2021年11月から約4カ月にわたり実施。2022年1月20日には災害時緊急輸送バスに関する協定を千代田区、日の丸自動車興業、東日本旅客鉄道と締結済。
- 2021年11月、富士山噴火による火山灰降灰を想定したビル運営管理の行動手順を策定。対象エリアは大丸有エリア。噴火とその後の気象庁の降灰予報、実際の降灰状況などに応じたビル機能の維持・避難誘導・帰宅困難者受入等に関するタイムラインの他、必要資機材や備品を選定。
|
- 2022年5月~2022年10月まで、丸の内仲通りの道路植栽帯の一部を利用した「レインガーデン」の実証実験を実施。豪雨時にも道路冠水を抑制する等の効果が期待できることが確認出来たことから、実験後も継続導入。
- 前年度に引き続き、丸の内エリアでのコジェネレーションシステムの増強等に取組み。
- 災害対策機関での情報共有や帰宅困難者向け情報発信を行うプラットフォーム「災害ダッシュボードBeta」の実証実験を2022年12~2023年2月に実施。発災時、避難者向けに駅構内等でQRコードによる情報提供を行う想定で、千代田区等が発信する災害時退避場所・帰宅困難者受入施設・災害拠点病院等を掲出するデジタルマップ版を試作。また、将来に向けてライブカメラの収集・編成・配信の仕組みの実証実験を行い、千代田区と災害時の有用性につき確認。
- 2023年2月、「ザ・パークハウス晴海タワーズ」2物件で初の合同防災訓練を管理組合・自治会と協働して実施
|
- 前年度に引き続き、丸の内エリアでのコジェネレーションシステムの増強等に取組み。
- 2023年5月、杏林大学・三鷹市・NPO法人Mitakaみんなの防災と協働し「Craft Market @ 杏林大学」を実施
- 2023年9月、第97回「ひと×まち防災訓練」を実施。東京消防庁の他、同社としては初めて警視庁との連携による、オフィス街交通規制を伴う、丸の内エリアでの大規模訓練として実施。
- 2024年2月より、大手町・丸の内・有楽町におけるエリア防災の取り組みとして、千代田区と災害時のDX連携協定を締結し、「災害ダッシュボード」を社会実装。2018年より同プラットフォームの実証実験を重ねており、この度千代田区と情報連携に関する協定を締結。
|
TNFDの開示を通じて(2025年3月末)、気候変動対策および生物多様性に関する取り組みを統合的に捉え、生態系サービス喪失に伴うリスクの洗い出しを実施。また、洪水発生時に備えた止水板やエネルギー設備の上層階への配置に加え、都市生態系の脆弱性を踏まえ、より広域的かつ長期的な視点からレジリエンス向上に向けた取り組みの方向性を検討している。
|