退職金の相場はいくら?企業規模や勤続年数、業種別に紹介
2025年8月14日

退職時に受け取る退職金は、将来の生活設計や老後資金に大きく関わる重要なお金です。
「自分はいくらもらえるのか?」「企業や勤続年数によって違うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、退職金の相場について、企業規模・勤続年数・業種ごとの違いに着目し、「中央労働委員会」や「e-Stat 政府統計の総合窓口」などの公的データを基に分かりやすく解説します。
退職金の金額はどうやって決まる?

退職金の金額は、企業規模や勤続年数、業種などによって大きく異なります。
そもそも退職金は法律で支給が義務付けられているわけではなく、支給の有無や金額は、各企業の就業規則や退職金規程によって定められるものです。
一般的に退職金の支給額が決まる要素は、以下の5つとされています。
- 企業規模
- 勤続年数
- 業種
- 退職時の基本給や役職
- 退職理由
例えば、一般的に中小企業よりも大企業のほうが、退職金の支給額は高くなる傾向があります。
勤続年数が長いほど支給額も増加し、勤続5年未満の場合、企業によっては退職金の支給対象外となることもあるようです。
さらに、退職理由も重要な要素です。
自己都合退職よりも定年退職や会社都合退職のほうが、退職金の支給額は高額になりやすいでしょう。
近年では、従来の一律計算方式に代わり、業績や評価に応じた「ポイント制」を採用する企業も増えており、個々の貢献度や役職によって退職金が大きく変動するケースもあります。
ポイント制については、後ほど「退職金の計算方法は?」という章で解説します。
企業規模別 退職金の相場

まずは、退職金の相場を企業の規模ごとに紹介します。
大企業と中小企業では、退職金の支給額にどの程度の差があるのか、それぞれの平均額を詳しく見ていきましょう。
大企業の退職金相場
大企業※において、定年まで同一企業に勤め上げた正社員の平均退職金額は、以下のとおりです。
| 学歴 | 定年退職金の平均額 |
|---|---|
| 大学卒 | 2,140万円 |
| 高校卒 | 2,020万円 |
※調査対象が資本金5億円以上かつ労働者1,000人以上(介護事業所以外)の企業であるため、本コラムでは「大企業」として分類
資料:中央労働委員会「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査」より作成
大学卒で2,100万円を超え、高校卒でも2,000万円前後と、高い水準にあることが分かります。
中小企業の退職金相場
一方で、中小企業※における定年退職時の平均退職金額は、以下のとおりです。
| 学歴 | 定年退職金の平均額 |
|---|---|
| 大学卒 | 1,150万円 |
| 高校卒 | 974万円 |
※調査対象が従業員数10〜299人の都内中小企業であるため、本コラムでは「中小企業」として分類
資料:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」より作成
大学卒で1,100万円台、高校卒では1,000万円未満となっており、大企業と比較すると1,000万円前後の差があることが分かります。
勤続年数別 退職金の相場

続いては、勤続年数に応じた退職金の相場について、大企業と中小企業に分けて紹介します。
退職金は、勤続年数が長くなるほど支給額が増加するのが一般的です。
| 勤続年数(年齢) | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 10年(32歳) | 183万円 | 306万円 |
| 15年(37歳) | 403万円 | 585万円 |
| 20年(42歳) | 762万円 | 1,022万円 |
| 25年(47歳) | 1,186万円 | 1,488万円 |
| 30年(52歳) | 1,772万円 | 2,055万円 |
※調査対象が資本金5億円以上かつ労働者1,000人以上(介護事業所以外)の企業であるため、本コラムでは「大企業」として分類
資料:e-Stat 政府統計の総合窓口「令和5年賃金事情等総合調査 集計表」
13-1(大学卒、事務・技術労働者、総合職相当、会社都合)
13-2(大学卒、事務・技術労働者、総合職相当、自己都合)より作成
大企業では、勤続年数が20年を超えると退職金が1,000万円を超え、30年勤続では2,000万円を超える水準に達しています。
これは年功序列や終身雇用の文化が根強く残る大企業の特徴ともいえるでしょう。
| 勤続年数(年齢) | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 10年(32歳) | 113万円 | 145万円 |
| 15年(37歳) | 209万円 | 256万円 |
| 20年(42歳) | 347万円 | 408万円 |
| 25年(47歳) | 507万円 | 616万円 |
| 30年(52歳) | 751万円 | 776万円 |
※調査対象が従業員数10〜299人の都内中小企業であるため、本コラムでは「中小企業」として分類
資料:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」より作成
中小企業では、大企業と比較して退職金額が大幅に少ない傾向があり、30年勤続しても1,000万円を下回る水準にとどまっています。
これは、企業の財務体力や制度の整備状況が影響していると考えられます。
なお、自己都合退職の場合、会社都合退職に比べて支給額が0.5〜2割ほど減額される傾向にあります。
業種別 退職金の相場

企業規模や勤続年数が同じでも、業種によって退職金の支給額に違いが見られます。
ここでは、中小企業における業種別の退職金相場を紹介します。
| 業種 | モデル退職金額 |
|---|---|
| 建設業 | 930万円 |
| 製造業 | 1,108万円 |
| 運輸・郵便業 | 938万円 |
| 卸売・小売業 | 1,239万円 |
| 金融・保険業 | 1,940万円 |
| 生活関連サービス・娯楽業 | 1,054万円 |
| サービス業(ほかに分類されないもの) | 969万円 |
※調査対象が従業員数10〜299人の都内中小企業であるため、本コラムでは「中小企業」として分類
資料:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」より作成
特に金融・保険業では1,900万円を超えるなど、他業種に比べて高額であることが分かります。
これは業界全体の収益性や給与水準の高さが影響していると考えられます。
一方、建設業や運輸業などは相場が1,000万円未満であり、業種ごとに退職金制度の手厚さにばらつきがある点も注目です。
退職金額は、勤務先の業種によって大きく左右されるため、転職や就職の際にはその点も確認しておくと安心です。
退職金の計算方法は?

退職金の計算方法は、企業ごとに就業規則や退職金規程で定められており、主に以下の3つの方式があります。
- ポイント制退職金
- 給与比例制
- 定額制退職金
ポイント制退職金は、勤続年数や役職、評価、貢献度などに応じてポイントが加算され、「累積ポイント × 単価 × 退職理由係数」によって支給額が決まる仕組みです。
実績が明確に反映されるため、成果主義の企業に多く導入されています。
給与比例制は、退職時の基本給や最終月給を基に計算されるため、長く働くほど支給額が大きくなりやすいのが特徴です。
一方、定額制退職金はあらかじめ決まった金額が支給され、勤続年数ごとに固定された金額表が用いられることが多く、シンプルで分かりやすいという特徴があります。
退職金の受け取り方は?
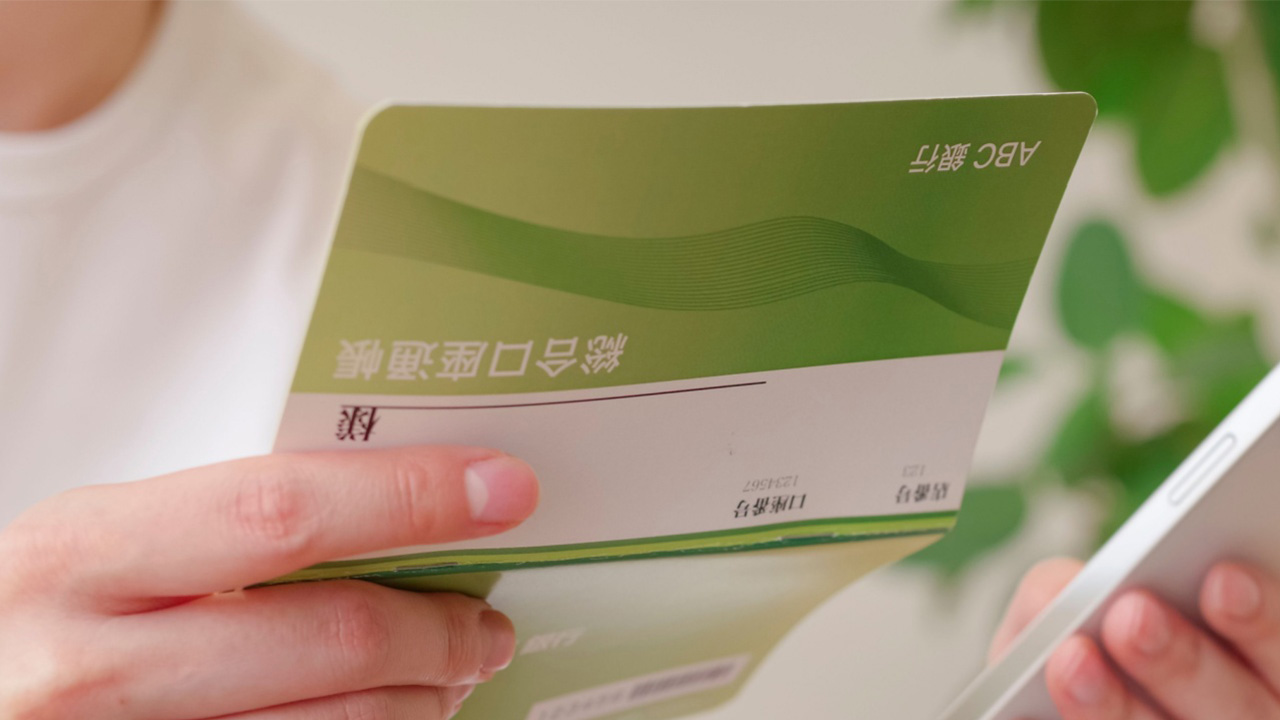
退職金の受け取り方には、大きく分けて3つの方式があります。
どの方法を選ぶかによって、税金の扱いや資金計画に大きな影響が出るため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
①退職一時金
最も一般的なのは「退職一時金」として全額をまとめて受け取る方法です。
受取時には退職所得控除が適用されるため、税制上のメリットが大きく、一定額までは非課税になる点が魅力です。
また、社会保険料もかからないため、多くの人がこの方法を選択しています。
②退職年金
「退職年金」として定年後に年金形式で少しずつ受け取る方法です。
公的年金などと合算して雑所得扱いとなり、所得税や住民税がかかるほか、健康保険料や介護保険料の負担が増えるケースもあります。
ただし、毎月の生活費を計画的に確保しやすい点はメリットです。
③退職一時金+退職年金
一定額を一時金で受け取り、残りを年金形式で受け取る方法です。「一時金+年金」の併用方式は一時金部分には退職所得控除、年金部分には公的年金等控除の両方を利用できるため、税制上のバランスが取れた方法と言えます。
ただし、企業によっては併用できない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
また、年金部分の受取額や期間、税負担の計算が複雑になり、税金や保険料が想定より増える可能性があるため、事前のシミュレーションが重要です。
まとまった退職金を受け取ると、老後資金を使いすぎてしまうリスクもあります。
受け取った退職金は生活費・医療費・予備資金などに用途を分け、必要に応じて資産運用を検討することをおすすめします。
退職金を賢く増やす方法はある?

退職金は老後の生活資金として非常に重要な役割を果たしますが、銀行に預けたままではほとんど増えません。
そのため、資産運用によって賢く増やす方法を検討することが大切です。
代表的な運用方法には、以下の7つがあります。
- 投資信託
- ファンドラップ
- 定期預金
- 個人向け国債
- 貯蓄型保険
- 外貨預金
- 株式投資
それぞれの運用方法はリスクやリターンの特性が異なるため、自分のリスク許容度や運用期間に合わせて商品を選ぶことが重要です。
例えば、定期預金や個人向け国債は元本保証があり、安定志向の方に向いています。一方、投資信託や株式はリスクを伴いますが、大きなリターンが得られる可能性もあります。
退職金の運用は、一括で投資するのではなく、複数の商品に分散してリスクを抑えつつ、長期的な視点で行うのが基本です。
必要に応じて、金融機関やファイナンシャル・プランナーに相談するのも良いでしょう。
退職金の資産運用で老後資金を形成しよう

退職金の金額は、企業規模や勤続年数、業種や退職理由などによって異なるため、まずは自分の退職金がどれくらいなのかを把握することが、老後資金計画の第一歩です。
仮に相場より少ない場合でも、早めに見積もりをしておくことで、貯蓄や資産運用によって補うことができるかもしれません。
逆に、相場以上の退職金を受け取った場合でも、適切に管理・運用しなければ、老後資金が目減りしてしまうリスクもあります。
そのため、運用商品や金融機関は自分のニーズに合ったものを選ぶことが大切です。
三井住友信託銀行では、ご退職後3年以内の方を対象とした退職金の運用をサポートする「退職金特別プラン」と、1年以内にご退職される方を対象とした「ご退職予定者向け特別プラン」をご用意しております。
退職金は一度きりの大きなお金です。無理のない範囲で分散投資を行い、老後の安心につなげましょう。
※この記事は2025年6月末時点の情報に基づいています。
当社では株式のお取り扱いは行っておりません。
その他本コラムに登場する金融商品の注意事項は、「退職金特別プラン・ご退職予定者向け特別プラン」のページ下部に掲載している注意事項をご覧ください。
監修者紹介
監修者 金子 賢司
資格 CFP®資格

プロフィール
東証一部上場企業(現在は東証スタンダード)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャル・プランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。
