夫婦で家計簿はつける?お金の管理・支出管理のポイントを紹介

結婚後は夫婦で生活費を共有することが多くなり、お金の管理について話し合う機会も増えていきます。
夫婦で収入や支出を共有するようになると、「家計簿をつけるべき?」「どうやって支出を管理すれば良いの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、夫婦でお金を管理する方法やお金を貯めるためのポイントを紹介します。
夫婦のお金はどちらが管理する?

夫婦のお金を管理する方法には、主に以下の3パターンがあります。
- 夫・妻のどちらかが管理する
- 夫婦の共有口座で管理する
- 費用ごとに分担して管理する
どの方法が良いかは、夫婦の収入のバランスや価値観、生活スタイルによって異なるため、一概には言えません。
大切なのは、お互いが納得し、ストレスなく続けられる方法を見つけることです。
まずは、それぞれの管理方法について、特徴と注意点を紹介します。
夫・妻のどちらかが管理する
夫婦の一方が家計全体を管理する方法は、支出の流れを一括で把握できるため、効率的に家計をコントロールできる点がメリットです。
毎月の生活費や保険料、住宅ローン、教育費などの支払いを1人がまとめて行うことで、無駄を発見しやすく、節約や貯蓄の計画も立てやすくなります。
お金の管理が得意なパートナーがいれば、計画的な貯蓄や支出の見直しもスムーズにできるでしょう。
ただし、もう一方が家計の状況を把握できないと、「今どれくらい貯金があるのか分からない」「何にいくら使っているのかが不明」といった不安や不満が生じやすくなります。
お互いが納得できる形で家計管理を続けるには、家計簿を共有したり、定期的に話し合いをしたりするなど、こまめなコミュニケーションを図ることが大切です。
夫婦の共有口座で管理する
夫婦で収入の一部または全てを共有口座に入金し、その口座から生活費や貯蓄、住宅ローン、教育費などを支払うパターンもあります。
特に共働きの場合、共有口座で一元的に管理をすれば、「家賃は夫、食費は妻」などと分けずに済むため、家計管理がシンプルになるのがメリットです。
一方、収入を全て共有口座に入れる場合は、いくつかのリスクに注意が必要です。
まず、個人的な趣味や交際費といった支出がオープンになり、お互いのプライバシーを保ちにくくなる可能性があります。
さらに、夫婦間で収入差が大きい場合、共有口座に多額の資金を貯蓄してしまうと、贈与税の対象となるリスクがあります。
夫婦間であっても、生活費や教育費として使う目的以外で、年間110万円を超える金額の移動があった場合は、贈与とみなされて課税対象となる可能性があるためです。
このリスクを回避するためには、共有口座に入れるお金を生活費や共通の支出分に限定し、収入の一部にとどめておくのが一つの方法です。
また、共有口座は一般的にどちらか一方の名義となるため、名義人に万が一のことがあった場合、口座が一時的に凍結されるリスクがあることも念頭に置いておきましょう。
費用ごとに分担して管理する
住居費・水道光熱費・保険料・食費などの費用の項目ごとに夫婦それぞれで分担して支払うスタイルも多く見られます。
夫が住宅ローンと光熱費を、妻が食費と子どもの教育費を負担するなど、収入差や生活スタイルに応じて無理のない形で調整できるのが魅力です。
ただし、家計全体の収支や貯蓄状況を把握しにくくなるというデメリットもあります。
「子どもの習い事の月謝が値上がりした」「物価の高騰で、食費の負担が増えてしまう」など、物価やライフステージの変化で負担のバランスが崩れることもあるため、定期的な見直しや情報共有が重要です。
夫婦のお金の管理で家計簿はつける?つけない?

家計簿をつけるかどうかは、夫婦間で意見が分かれやすいテーマです。
「細かく管理したい」という気持ちと、「面倒で続かない」という現実の間で迷うこともあるのではないでしょうか。
家計簿をつけるメリットと、つけない場合の工夫を知ることで、自分たちに合ったスタイルを見つけやすくなるでしょう。
ここでは、家計簿を「つける派」と「つけない派」それぞれの考え方を紹介します。
家計簿をつける派
家計簿を活用して支出や収入を細かく記録することで、家計の全体像が明確になるなどの考えから、家計簿をつける方もいます。
「思ったより外食費が多い」「サブスクが積み重なっている」など、無意識の支出を見える化できるため、無駄をなくしやすいです。
また、毎月の固定費と変動費を分類することで、生活コストの見直しや節約計画も立てやすくなります。
将来のマイホーム購入や子どもの教育資金など長期的なライフプランを立てている夫婦にとって、家計簿は心強いツールです。
家計簿はつけない派
「毎日細かく記録するのは性に合わない」「管理に時間をかけすぎたくない」という考えで、あえて家計簿をつけない夫婦もいます。
ただし、家計管理をまったくしないわけではなく、大まかに支出を把握する「ほどほどの家計管理」を行う方が多いようです。
例えば、「毎月の生活費は10万円まで」「外食は週2回まで」といったルールを決めておき、その範囲でやりくりするスタイルは、無理なく続けやすい方法として人気です。支出の自由度を保ちつつ、過度なストレスを感じることなく家計のバランスを整えることができます。
また、クレジットカードの利用履歴や銀行アプリの月次レポートなどを活用することで、大まかに出費を把握することも可能です。
最近では、スマートフォンで簡単に記録できるアプリや、クレジットカードや銀行口座と連携して自動で分類・集計してくれる家計管理ツールも充実しています。
夫婦で共有アカウントを利用すれば、どちらが何に使ったかもすぐに確認でき、透明性の高いお金の管理ができるでしょう。
夫婦の支出管理で賢くお金を貯めるポイント

将来への不安を減らすためには、収入を増やすことだけでなく、日々の支出をしっかりとコントロールすることが重要です。
ここからは、夫婦で協力しながら支出を管理し、効率良くお金を貯めていくための具体的なポイントを紹介します。
将来のライフイベントに合わせた目標を決める
夫婦生活のなかでは、子どもの進学やマイホームの購入、車の買い替え、老後の生活資金など、さまざまなライフイベントに備える必要があります。
将来の大きな支出に対応するには、早い段階で目標を設定し、計画的に準備していくことが必要です。
例えば、「3年後にマイホーム購入の頭金を300万円貯めたい」「教育資金として毎年20万円を積み立てたい」など具体的な金額と期限を設定すると目標が明確になり、達成までの道筋が見えてきます。
夫婦で同じ目標を持てば、達成に向けてお互いの意識を高め合うことができるでしょう。
固定費や無駄な支出を見直す
節約を成功させるためには、固定費の見直しから取り組むのが効果的です。固定費とは、毎月、毎年など、定期的にほぼ定額でかかる支出を指します。
スマートフォンの料金プランや生命保険・医療保険の契約内容を見直すことで、毎月の支出を大幅に削減できる可能性があります。
また、複数契約している動画配信サービスや使っていないジムの会費など、不要なサブスクリプションは早めに解約しましょう。
家計簿アプリで「見える化」する
家計簿アプリなどで家計を見える化すると、日々の支出を把握しやすくなります。
最近では、スマートフォンで手軽に支出を記録できるアプリや、銀行口座・クレジットカードと自動連携できる家計管理サービスなど、手間をかけずにお金の管理ができるツールが充実しています。
例えば、三井住友信託銀行が提供する家計簿・資産管理アプリ「スマートライフデザイナー」は、毎月の支出を見える化できるだけでなく、資産の推移や将来のライフプランも一括で管理できるツールです。
細かい作業が苦手な方にも扱いやすい設計となっています。
無駄遣いの傾向を把握しやすくなり、「使いすぎた月は来月調整しよう」といった柔軟な対応も可能になるでしょう。
貯蓄と生活費を分ける
お金を無理なく貯めるには、「使って良いお金」と「貯めるべきお金」を分けて管理するのもポイントです。
代表的な方法としては、給料が振り込まれたらすぐに一定額を貯蓄用口座へ移す「先取り貯蓄」という方法があります。
「余ったら貯金」ではなく、「先に貯めて、残った金額で生活する」という考え方に切り替えることで、安定的な資産形成がしやすくなるでしょう。
また、生活費・旅行費用・教育資金・マイホーム費用など、目的ごとに口座を分けるのも効果的です。
目的をはっきりさせることで無駄遣いを防ぎやすくなり、「このペースで貯めればいつ頃達成できそう」という進捗確認もしやすくなります。
支出の優先順位を明確にする
家計を見直す上で重要なのは、支出の取捨選択ができているかどうかです。
全ての出費を同じように扱うのではなく、「本当に必要な支出」と「満足感を得るための支出」をきちんと区別することが求められます。
例えば、家賃・光熱費・保険料・医療費・子どもの教育費などは、生活を維持する上で欠かせない支出です。
一方で、趣味のアイテムや高級な外食などは、満足感を得るための支出に該当します。
「何となく買ってしまった」「その場の気分で使ってしまう」といった支出の積み重ねは、気付かないうちに家計を圧迫してしまいます。
夫婦で協力し、貯蓄目標を達成するためには、それぞれが日頃から貯蓄の必要性を意識して、支出に優先順位を付ける習慣を身に付けましょう。
夫婦で定期的に話し合う
どんなに計画的に家計を管理していても、夫婦間でお金の価値観にズレがあると、ストレスや不満が生まれやすくなります。
お金に関するストレスを防ぐには、定期的に家計について話し合う機会を設け、お互いの認識を合わせることが大切です。
月に1回程度、収支の振り返りや貯蓄目標の進捗確認をすれば、「来月は旅行があるから支出が増える」「新しく保険を見直したい」といった話もしやすくなるでしょう。
日常の会話がお金の話ばかりになってしまうと、かえって疲れてしまうこともあるため、コーヒーを飲みながら10分だけ話すなど、無理のない形で継続するのがポイントです。
夫婦のお金の管理に家計簿を使おう!将来設計は大切
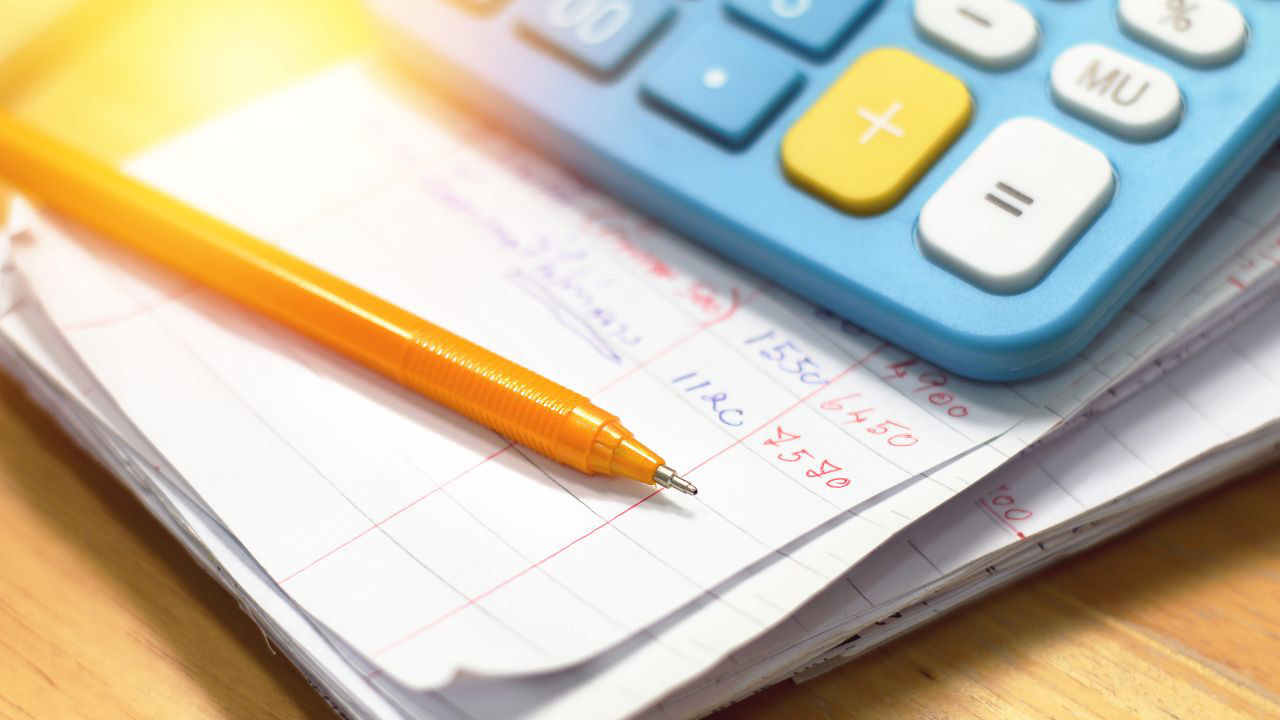
家計簿アプリなどを活用して家計を見える化すると、負担やストレスなく、日々の支出や貯蓄の状況が把握できるようになります。
無駄な支出を抑えたり、貯蓄の目標が立てやすくなったりするため、将来への安心感にもつながるでしょう。
「5年以内にマイホームを買いたい」「老後資金を積み立てよう」などの将来設計は夫婦で共有するようにし、家計管理はお互いに無理なく続けられる方法で継続することが大切です。
※この記事は2025年8月末時点の情報に基づいています
監修者紹介
監修者 金子 賢司
資格 CFP®資格

プロフィール
東証一部上場企業(現在は東証スタンダード)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャル・プランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。
アプリ「スマートライフデザイナー」について
ご利用にあたってのご注意事項等は当社ホームページをご確認ください。
