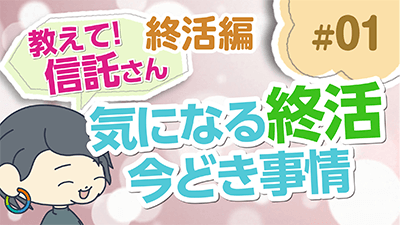生前贈与は早く始めるほど効果的!生前贈与のメリットや注意点を解説
自分の財産を他者に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」があります。相続対策の方法というと「遺言」をイメージしがちですが、生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与も有効な相続対策の一つです。ただし、生前贈与の仕方によっては贈与税や相続税の課税対象になるなど注意点もあり、どのように贈与するかも大切です。
本記事では生前贈与を活用するメリットや効果的な生前贈与の方法、注意点などについて解説します。
生前贈与の効果とは?
そもそも生前贈与とは、存命中に財産を他者に贈与することです。つまり、自分が生きている間に自分の財産を他者に無償で与えることを指します。相続は、自分(被相続人)が亡くなったあとに自分の財産が相続人へ引き継がれる点が大きな違いです。
このように聞くと、相続と生前贈与は亡くなったあとに財産を引き継ぐか、生きている間に引き継ぐかが異なるだけと考える人もいるかもしれません。しかし、生前贈与をすれば相続時の財産を減らす効果があります。
事前に財産を贈与することで自分が亡くなったときの財産(相続財産)が少なくなるため、相続時の財産にかかる相続税も軽減される可能性があるのです。もちろん生前贈与の場合でも、基本的に贈与を受けた人(受贈者)は贈与税を払う必要があります。
ただ、税制上の一定要件を満たせば贈与税がかからなかったり、かかっても税額を抑えたりすることが可能です。なお、生前贈与は大きく分けると「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の2つがあります。
| 相続時精算課税制度 |
|
|---|---|
| 暦年課税(暦年贈与) |
|
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受ける側(受贈者)が税務署へ申告をします。また、一度、相続時精算課税制度を選択してしまうと暦年課税に戻すことはできません。本記事では「相続時精算課税制度」ではなく、「暦年贈与」として生前贈与の説明を進めていきます。
生前贈与のメリット
ここからは、生前贈与の効果やメリットを具体的に確認していきましょう。
相続税の軽減効果がある
上述したように、生前贈与は相続時の財産を減らす効果があります。相続税は、相続時の課税遺産総額に対して課税されるため、相続時の財産を減らすことができれば、税金を軽減することが期待できるでしょう。相続税の細かい計算方法についての説明は割愛しますが、相続税は基礎控除額を上回った部分に対してかかるのが基本です。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わり、次のように計算されます。
- 相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
- 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
仮に、法定相続人が1人であっても3,600万円の基礎控除があります。
- 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
生前贈与をして少しずつ自分の財産を減らしていけば、将来的に相続財産が基礎控除額と同等か基礎控除額を下回るようになった場合は、相続税がかかりません。
減税効果が累積する
相続だけでなく、贈与にも基礎控除があります。暦年課税の場合の基礎控除額は、110万円です。そのため、1月1日~12月31日までの1年間で贈与を受けた場合は、受贈者1人あたり110万円までが非課税となります。なお、贈与税は以下のような計算式で算出可能です。
- 贈与税:(贈与された金額-基礎控除110万円)×贈与税率
たくさん相続財産を減らしたい人にとっては、1回あたりの節税効果は決して大きくはありません。それでも贈与税は、1年ごとに課税関係が清算されるため、毎年分割して贈与することでその効果が累積し、贈与時および相続時の税負担を軽減できるメリットがあります。
税制改正のリスクを回避できる
税法が毎年のように改正されていることをご存じでしょうか。本記事は、2022年時点の税制に基づき説明していますが、将来的に贈与や相続に関する税制が変わり、効果が期待できなくなる可能性は否めません。
贈与税の暦年課税は、1年ごとに課税関係が清算されるため、贈与のあった年の税制で課税関係が決まります。思い立ったときに生前贈与をしておけば、将来の税制改正等による効果の減殺リスクを避けることが期待できるでしょう。
贈与時期を選択でき、評価額の上昇の影響を防げる
贈与は、存命中であればいつでもできることもメリットの一つです。所有する財産の種類によっては、例えば有価証券など将来的に価格(評価額)が上昇する可能性があります。それらの財産が値上がりすると思われる前のタイミングで贈与をすれば、将来的に相続財産の評価額が上がり、支払うべき相続税が増えるのを防げます。
ただし、贈与してから3年以内に相続が発生した場合は、税法上、その贈与分は相続財産として加算されるというルールがあります。この場合でも相続財産として持ち戻す価格は、贈与時の評価額となるため、贈与後に評価額の上昇の影響は受けません。結果的に、相続税の軽減につながることが期待できるでしょう。
特定の人に特定の財産を残すことができる
財産ごとに贈与したい特定の人がいる場合は、生前贈与を活用することで確実にその財産所有権を移転できます。相続の場合でも遺言で「誰にどの財産を相続させるか」を決めることは可能です。しかし、相続内容を不服とする相続人がいる場合、トラブルに発展する可能性があるでしょう。
一方、生前贈与であれば自分が存命しているため、自分がどのように財産を相続させたいのかを家族に丁寧に伝え、納得してもらうことも期待できます。なお、のちに相続が発生したとき、生前贈与した財産が法定相続人の遺留分を侵害することになって請求されるケースもあり得ます。
しかし、仮に遺留分侵害で請求されることがあっても「遺留分侵害額の請求権」となり、遺留分侵害額に相当する金銭を請求されるだけで、贈与した財産自体の所有権は受贈者が保持可能です。そのため、特定の人に与えたい意思は尊重されます。
お一人おひとりに合った終活のヒントとなる情報をお届けします。
YouTube公式チャンネル内の動画が再生されます。
ご利用にあたっては、ソーシャルメディアご利用規約をご確認ください。
なお、上部動画が正常に再生されない方はこちらからご覧ください。
生前贈与を上手く活用する方法は?
生前贈与には、さまざまなメリットがあることが理解できたでしょうか。効果的な生前贈与をするためには、贈与の仕方も大切なポイントとなります。ここからは、生前贈与を上手く活用するためのポイントを3つ紹介します。
多くの人へ贈与する
多くの人に贈与することで税額が変わります。贈与税の基礎控除は、受贈者それぞれに適用されるため、「基礎控除110万円×受贈者の人数分」の財産を非課税で贈与することができます。贈与税は、累進課税となるため、例えば一括で1,000万円を贈与すると、税率は30%(特例贈与財産の場合)と非常に高くなります。
そのため、非課税で贈与を受けられることは受け取る側にとっても税負担の軽減につながります。具体的に、1,000万円を贈与したケースで、受贈者数の違いで税負担がどのように変わるか確認してみましょう。なお、ここで示す例は親や祖父母などの直系尊属から成人している子どもや孫への贈与の場合に用いられる「特例税率」で計算します。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じ、所定の控除額を考慮の上、税額を計算します。詳しくは国税庁をご覧ください。
| 受贈者 | 税率 | 控除額 | 計算式 | 贈与税額 |
|---|---|---|---|---|
| 1人 (1,000万円) |
30% | 90万円 |
|
177万円 |
| 2人 (500万円×2) |
15% | 10万円 |
|
97万円 (一人あたり48万5,000円) |
| 5人 (200万円×5) |
10% | ― |
|
45万円 (一人あたり9万円) |
暦年贈与を活かす
一度に多額の贈与をするのではなく、毎年110万円の範囲内で分割して贈与することでも税負担を軽くする効果があります。毎年非課税で贈与できる財産は、基礎控除の110万円までですが、例えば10年間継続すれば1,100万円です。また、3人に毎年110万円ずつ贈与した場合は、10年間で合計3,300万円を移転できます。
ただし、定期贈与とみなされ贈与税が課税される場合があることには注意が必要です。定期贈与とは、はじめから多額の財産を贈与する予定にしているけれども、税金がかからないように定期的に分割して贈与することを指します。定期贈与とみなされないためには、毎年、贈与の意思決定をすることが必要です。毎回、贈与のたびに贈与契約書を作成するなど注意しましょう。
将来値上がりしそうな財産から贈与する
メリットの項目で説明した通り、万一贈与してから3年以内に贈与した人の相続が発生した場合、贈与時の評価額で相続財産として加算されます。そのため、将来値上がりしそうな財産から優先的に贈与することで相続税の負担軽減効果が高まります。
直系卑属への贈与税非課税制度の活用も考えよう
ここまで暦年贈与を中心に生前贈与の効果や活用法を説明してきましたが、その他の贈与税非課税制度の活用もおすすめです。直系尊属から教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金の贈与制度を活用すれば、大きな非課税枠があるため、相続税軽減効果も高くなります。該当する親族がいる場合には、これらの制度の活用も検討してみましょう。
それぞれに非課税となるための要件や上限金額が決められています。しかし、基本的に直系尊属(祖父母や父母など)から直系卑属(子や孫など)に対して一度にまとまった金額を贈与する点は同じです。例えば、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与なら贈与された金銭は、信託銀行など金融機関へ預けて専用口座で管理してもらうため、名義預金などといったリスクを避けられます。
教育資金の一括贈与
使途を教育資金に限定した一括贈与で、受贈者1人につき1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで非課税となる制度です。受贈者が30歳未満、かつ前年所得1,000万円以下が要件となっています。適用は、2023年3月31日までです。
なお、受贈者が30歳に達した際に学校等に在学していなかったり、贈与者が死亡したりした場合など教育資金として使っていない残額に対しては、贈与税または相続税の対象となることがあります。
結婚・子育て資金の一括贈与
使途を結婚・子育てに限定した資金の一括贈与で、受贈者1人につき1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで非課税となる制度です。受贈者が18歳以上50歳未満、かつ前年所得1,000万円以下が要件となります。適用は、2023年3月31日までです。
なお、受贈者が50歳に達したり、贈与者が死亡したりした場合など、結婚・子育て資金として使っていない残額に対しては、贈与税または相続税の対象となることがあります。
住宅取得等資金贈与
住宅の新築、取得または増改築等の資金として贈与を受ける場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで非課税になる制度です。受贈者が18歳以上で、かつ贈与を受けた年の所得が2,000万円以下(一定の住宅要件を満たす場合は1,000万円以下)であることが要件です。2023年12月31日まで適用されます。
なお、上記2つの制度とは異なり、以下のような細かい要件があるため、利用する際は注意が必要です。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに受贈資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする
- その後遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれている など
生前贈与の注意点
生前贈与をする際には、以下の3つのような注意点もあるため、しっかりと確認しておきましょう。
名義預金に注意
そもそも贈与は、贈与者が一方的に行うものではありません。贈与者と受贈者の双方で「あげます」「もらいます」といった合意に基づき行うことが必要です。そのため、一方的に贈与して受け取った側が与えられたことを知らなければ、贈与とはみなされません。
例えば、贈与者(親など)が自分の資産で受贈者(子どもなど)名義の預金口座を開設し、受贈者がその存在を知らないことはよく聞く話です。このような場合、その預金口座は「名義預金」として相続税の課税対象になる可能性があります。
名義預金とみなされないためには、贈与をするたびに、誰が(贈与者)、誰に(受贈者)、いつ(贈与時期)、何を(贈与財産の内容 )、どうやって(贈与の方法)贈与するかを明確にした贈与契約書を作成することが大切です。
遺留分侵害額請求に注意
生前贈与は、贈与者の存命中の贈与となるため、遺言と比べて相続人同士のトラブルを避けやすいと前述しました。しかし、やはり特定の人に偏った贈与をしていると相続の際に相続人同士でもめる可能性があります。贈与を行う際は、後日、受贈者が遺留分侵害額請求をされ、金銭負担が生じることになる可能性がある点に注意しながら実行することが大切です。
老後の生活費や介護費用不足に注意
生前贈与は、いつ起こるか分からない相続に備えて節税対策として行うケースもあります。しかし、自分が思っているよりも存命期間が長かったり、贈与をしすぎたりした場合は、自身の老後資金や介護資金が不足してしまいかねません。子どもや孫のために贈与して、税負担を抑えるつもりにもかかわらず、かえって子どもや孫に金銭サポートを頼ることになっては本末転倒です。
どれだけ長生きするかは、予測できないため、誰にも分かりません。そのため、生前贈与は老後設計と同時に計画することが大切です。
思い立ったら早めに贈与することも大切
生前贈与は、自分の希望通りに財産を引き継がせられるだけでなく、上手に活用すれば相続税を軽減できるメリットがあります。そのため、相続対策の一つとして取り組むのもおすすめです。しかし、生前贈与の効果を得るためには、贈与の仕方に気をつけることも大切です。本稿で紹介したポイントに加え、将来の税制改正リスクを考慮し、早めに対策を講じていきましょう。
執筆者紹介
續 恵美子(つづき えみこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(CFP)
生命保険会社にて15年勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。「生きる上で大切な夢とお金のことを伝える」をミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
相続・贈与に関するお悩みは
お近くの店舗・オンラインで無料でご相談いただけます。
三井住友信託銀行では、高い専門性と豊かな経験をもった財務コンサルタントなどの専門スタッフがじっくりお客さまのご相談を承ります。
店舗でのご相談はもちろん、オンライン相談も可能です。オンライン相談であれば遠隔地にお住まいの親御様やお子様もご一緒に相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。